
コラム
BLOGブログ
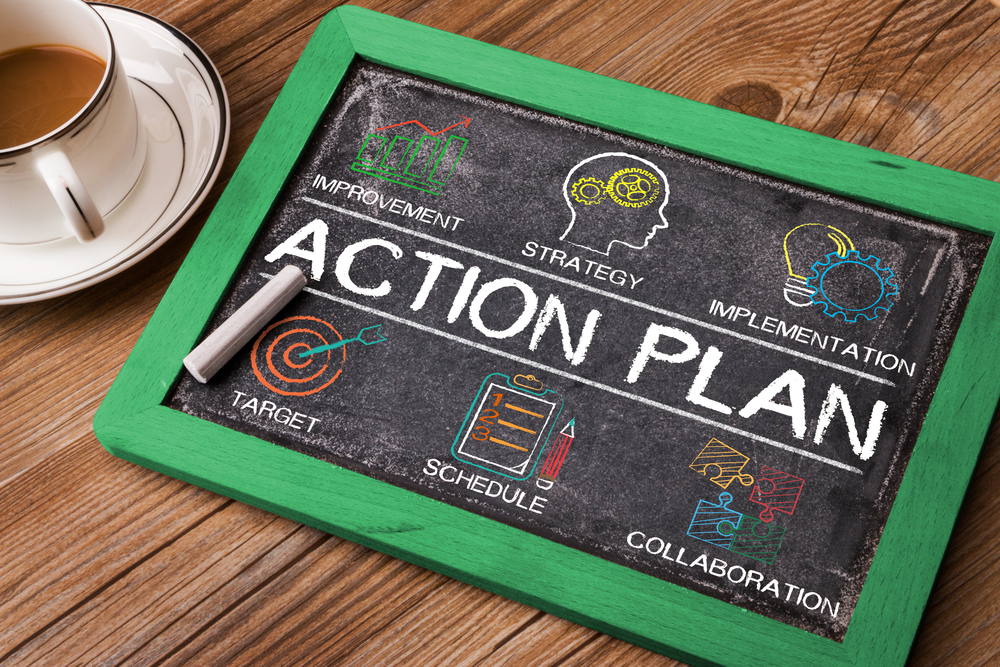
営業目標の達成は、営業部門に所属するマネージャー、そしてメンバーに課せられた最大のミッションです。ですから、営業目標の達成が難しい状況に陥ると、メンバーからマネージャーまで営業組織の全員が“頭を抱えて”しまいます。
これは、継続的な活動から、当月のその“地点“で見たときの成果についての状況ですので、ここで改善ができないとなると、翌月・3か月先・1年後とそれぞれの“地点”での成果も見えにくくなってしまいます。
営業目標に対して予測ができ、一定の安定した成果を達成するためには「具体的なアクションプランに落としこんだ営業管理」が必須となります。
今回は、初めの方にもできるだけわかりやすい内容にして、アクションプランの立案方法と、その実行についてお話ししていこうと思います。
目次
まず、営業目標達成に必要なアクションをフローにして、目標から逆算して棚卸・洗い出しをしてみてください。ここから始まります。
営業目標が「新規獲得10件」だとすると、その前には、まず“クロージング”のアクションが必要なはずです。
同様に、クロージングの前には“見積もり提出”のアクション、その前には“訪問アポ”さらに前には“電話でのアポイント”…といった具合です。
この「アクション」とステップは、企業ごと組織ごとに異なるので、自社の営業戦術やプロセスに合ったアクションを確認してください。
次に、過去の営業活動のデータから、設定した各アクションにおける歩留まり率(アクションをする前の数からアクション後の数がどう変化するかについて、%で示した数値)を確認し、その歩留まりを踏まえた上で、必要となる“アクション前”の必要な行動量を算出します。
先ほど例としてお話しした「営業目標:新規獲得10件」を例に、それぞれのアクションにおいて活動量が、どの程度必要なのかシミュレーションをしてみます。
■行動量算出の例(括弧内は歩留まり)
営業目標:新規獲得10件
クロージング:40件(25%)
見積もり提出:80件(50%)
訪問アポ:160件(50%)
テレアポ:3,200件(5%)
という具合です。このように可視化してみると、アクションに対しての活動量はもちろん、現状とのギャップを明確に認識していくことも出来ますね。
各アクションに必要な件数が算出できたら、それを月次・週次・日次などで分解し、営業メンバーの行動目標計画に落とし込んでください。
「テレアポ3,200件」と合計の行動量だけを示すと、とても大きな遠い目標に感じられてしまいますが、日次で分解して「1日テレアポ20件をXX名で」というように、期間で分解することで達成のイメージが持てます。

アクションプランの進捗状況は、可能な限りこまめに定期的にチェックしてください。
プランのチェック空いてしまうと、進捗遅れに気づくのが遅れ、計画との乖離がおき、軌道修正していくことが困難になるからです。
進捗管理を確実に行うために、各営業担当者が状況を正確に記録している必要があります。これはとても重要なことでここでの数値が、もし、不正確なものですと、チェックをする際の数値が正確でないため、判断そのものを誤る可能性も出てきます。
SFAなどの支援ツールを導入し、入力や集計が手間なくできるような体制を整えておくことも一つの手段です。
もし、進捗が遅れている担当者がいた場合、個別に面談し、周りに他の人間がいない状態でフィードバックをするようにしてください。
他の人の目があるところでフィードバックをすると、周囲の目がある中で本人の立場もあるため、本音を引き出せないばかりか、時には「バカにされた」「恥をかかされた」と受け取られてしまい、せっかく時間を作って準備をして行ったフィードバックが素直に受け入れられないばかりか、感情的になり、それ以降の関係性にも“しこり”を残してしまう可能性があります。
また、内容が整理されていない・具体的になっていないフィードバックをしたり、長時間に渡ってフィードバックすることも、当然避けて下さい。
基本は、感情的にならず進捗に達していないことを事実として指摘する。その原因をヒアリングした上で、できれば、自発的に本人から対策を挙げるように誘導していくことです。
大前提ですが、「進捗が遅れていること」を責めているのではなく、「一緒に解決しよう」としている姿勢を見せることが重要です。
たとえば、トップダウンなどで“無謀な予算”が押し付けられたという状況でもなければ、計画(プランニング)に沿った“相応”の努力をしていけば実現できる営業目標が設定されているはずです。
このような状況下で、日々のアクションプランについては、着実に実行しているのにもかかわらず、目標の達成が難しくなってしまったとき、どのように改善をするべきでしょうか。
予算は当初の予定から大きく変化しておらず、アクションも着実に行っているという状況では、「アクションの内容や質、または、そもそもの考え方や方向性に間違いがある」というケースが多くみられます。
「目標に対しての進捗が著しくない」と焦りがでて、無闇に“行動量を増やしたりする”もしくは“アクションした際のフェーズアップの定義を守っていない”など、細かくみていくと、必ず何かしらの「要因」が見つかるはずです。
進捗が思わしくないときこそ、一度“基本”に立ち返って、何が“要因”となって、Gン材の状況になっているのかを、冷静に分析することが大切です。
また、組織全体のアクションプランの各項目の数値を振り返り、前年や前月と比較して、数字に変化がある指標とそのアクションについて、検証をすることも大切です。
たとえば、昨年に比べてクロージング段階での歩留まり率が、悪くなっていたとしましょう。
要因として、「営業のクロージング力が低下している」ですとか、「市況が悪化し、顧客の予算が縮小している」といった仮説が立てられます。
もし、本人へのヒアリングや市場の分析にて、仮説が正しいとなれば、「クロージング商談には上長が同行する」「期間限定の値引きキャンペーンを実施する」といった打ち手を考えられます。
どのような改善も、結論、原因が明らかにならなければ効果的な対策は考えられません。状況が思わしくないときこそ、冷静に分析する習慣をつけると、必ず改善の役に立つはずです。
営業目標を達成するためには、定性的な定義による不明瞭なアクションプランではなく、定量的で誰にでもわかりやすい具体的なアクションプランの策定が欠かせません。
数値を元にした論理的、かつ、合理的なアクションプランを立てて、スマートに営業目標を達成できる組織づくりをしていきましょう。
"UPWARD"について資料をダウンロード
以下のフォームにご入力いただくと、ダウンロードURLを記載したメールをお送りします。