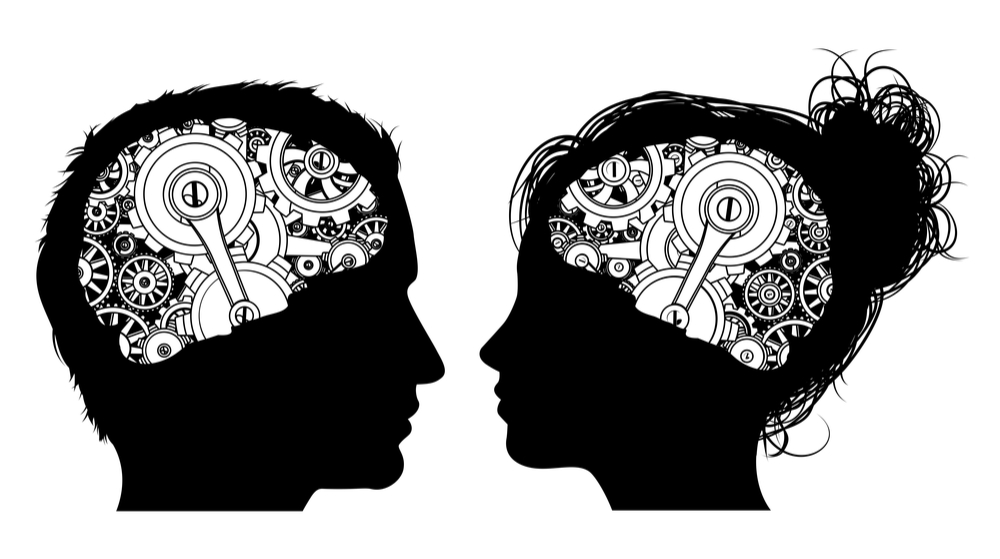
コラム
BLOGブログ

自社のサービスや商品を販売し、継続利用してもらうための営業活動。何度も訪問し担当者と仲良くなってもなかなか契約に至らない…といった悩みを持っている方も多いのではないでしょうか。たとえ自信のあるサービスや商品であっても、適切な営業手法を理解し商談を進めなくては、受注に至る確率は上がりません。そこで今回は「受注率」を上げるためのヒントをご紹介します。
目次
受注率を上げる方法というと、どんなことを思い浮かべますか。
良い提案をするとか、ヒアリングが大切という話にすぐ入りがちですが、その前に、「現在、適切な商談がどれだけあるか」も見直しておくべきです。なぜなら、そもそも受注につながらないような”名ばかり商談”ばかりでは、いくら営業マンのスキルを向上させても受注率は上がらないからです。それでは、「適切な商談」とはどんな商談で、どのようにしたら増やせるのでしょうか。
「適切な商談」を増やすには
「ルートセールス/訪問営業の訪問件数を増やすには(URLリンク)」でも同様のことをご紹介しましたが、想定しているターゲット像からかけ離れた商談先は受注につながりにくいものです。そうした商談に時間を割くより、ターゲット像に近い他のお客様にアプローチする方が建設的です。
ちなみに、ターゲット像と実際に売上の多い商談先が大きく異なる場合は、そのずれが発生している理由や、今後どちらをターゲットとしていくのかを見直す必要があります。
以前は興味のなかったお客様のところへ行ったら、「ちょうど話を聞きたいと思ってたんだよ!」なんて、タイミングのいい商談もありますね。
こうした「グッドタイミング」は、待っているだけではなかなか来ません。
お客様の決算期や繁忙期などを把握しておき、検討してもらえそうな時期を見計らって顔を出すなど、積極的に「グッドタイミング」に会う機会を作っていくことが大切です。
ただ、多くの訪問先のタイミングを全て把握しておくのは難しいもの。
人は、顔を合わせた回数が多いほど好意を持つ傾向があるので、タイミングを狙いすぎて訪問の間を空けてしまうよりは、ある程度の頻度で顔を出しておいた方が良いでしょう。
訪問先に顔を出しても、ご用聞きだけでは商談は増えません。今すぐ○○したい!というお客様でなくても、相手が持っているであろうニーズや将来像を想定した提案をこちらから持っていってみましょう。
「これいいね」と言ってもらえれば、商談につなげるチャンスです。
高い受注率を誇るある企業では、新規営業の4割以上が部長クラス以上との商談だそうです。権限のない現場担当者とは商談の前に意思疎通をはかっておき、商談の際は上席のキーパーソンに同席してもらうようにすれば、効率のよい商談を行えます。
前半では「適切な商談の増やし方」についてご紹介しました。ここからは、ルートセールス/訪問営業に限りませんが、受注率を上げる商談の進め方について簡単にお話ししましょう。
商談の冒頭では、まず課題を共有する、というのはご存知の方も多いと思いますが、事前情報がどれだけあっても、まずは、「お客様自身に課題を口にしてもらう」ことが大切です。
自分自身で言葉にすることで、改めて現状のニーズ・課題を再認識して危機感を感じてもらうことができ、解決法=商品に対する期待感が高まります。
購買心理学によれば、人が購買するときの決め手は「苦痛からの解放」か「快楽の追求」のどちらかの欲望です。
ですから、お客様が何を苦痛と感じているか、何を快楽と感じるのかをあらかじめチェックしておき、この2つの欲望を自社商品と関連づけて提案してください。
ex.「頑固なシミが落ちないということでしたが、この洗剤なら頑固なシミもささっと落ち、さらに次のシミもつきにくくなるので、洗濯が楽になりますよ」
提案する際は、その商品を買うことで具体的にお客様の苦痛がどうなくなるのか、どんな快楽が得られるのか、イメージしやすい言葉で伝えることで、より大きなメリットを感じてもらうことができます。
商談後もまだまだ気は抜けません。
なぜなら、たとえば、BtoB向けの商品Aを発注してもらう場合、担当者は上司や関連部署にAの機能、メリット、Aを選んだ理由などを理解してもらい、実際にAを使うメンバーの要望を取り入れ、社内調整をし、稟議書を出し、予算を確保し、Aを導入する——というように、たくさんの壁を乗り越えなければならず、「担当者の手応えは良かったのに、社内で折り合いがつかずに失注」という事態も容易に起こりえるからです。
商談後は、担当者が社内展開する際に”武器”となる情報を渡し、積極的にサポートをしていきましょう。”武器”となる情報とは、他部署に提出するための参考資料などのことです。
このとき、決裁権を持つキーパーソン、自社商品が魅力的/不満に思われている点、会社の体質、将来の方向性などが分かっていると、より攻めやすくなります。
次の「受注単価を上げるには」でもお話ししますが、買い手は、金額に見合う十分なメリットがあると納得すれば予算を確保するものです。ですから、予算を理由とする失注が多い場合には、商談の最初に課題を共有し、その課題を解決するメリットがあるものとして自社商品を提案できているかを改めて見直してください。
ここまで、受注率を上げるポイントを簡単にご紹介してきました。
商談開始〜受注の一連の流れは、お客様に関する情報量が多ければ多いほど、スムーズに進めやすくなります。商談の場だけで聞き出しきれない情報は、ルートセールス/訪問営業の強みを生かして日頃の訪問時に収集し、商談の成功に生かしてください。
チームで大きな目標数字を達成するためには、目標を細分化していくことが必要です。細分化とは、「○件の受注を得るには○件の商談が必要なので、まずは○件の商談を作ることを目標にする」というように、目標をブレイクダウンしていくことです。
同じように、商談においても、開始から受注までには様々なフェーズがあります。一口に「受注率が低い」といっても、「見積もりを出すまで行かない」のか、「予算でNG」なのかでは、対策も違ってくるはずです。
ですから、商談フェーズに応じた数字や目標を可視化して、ボトルネックを把握し、対策を行っていく。当たり前ですが、これが最も確実に受注率を上げる方法です。
また、営業状況を分析して受注率アップのヒントを探す際は、グラフだけではなく地図上に営業状況を表示し、全体を俯瞰してみるのも有効です。
これはいわゆるエリアマーケティングですが、ルートセールス/訪問営業では、地理的要素が売上を左右することが珍しくありません。地図上で視覚的に営業状況を把握すると、今まで気づかなかったウィークポイントが見えてくることがあります。
さらに、商談フェーズをマッピングして次の接触タイミングを見落とさないようにしたり、品目別の売上をマッピングして横展開の可能性を見つけたりと、受注率の改善だけでなく、販売機会の増加や受注単価アップにつながるヒントも見つかります。
また、ルートセールス/訪問営業において今後の戦略を考える際には、ビッグデータや競合他社のシェア率などのデータと自社の営業状況を地図上で重ね合わせる方法も役立ちます。
そうすることで、まだニーズが眠っていそうなエリアを次の注力先にして、より受注率が高そうなお客様に集中してアタックしていくことができます。
最初にお伝えした通り、受注率をアップさせるには、基本的には商談フェーズのボトルネックを把握して地道に対策を行っていくしかありません。
ただ、エリア要素が大きく関わるルートセールス/訪問営業では、地図を使って様々なデータをマッピングし、エリアマーケティングを行うことで、受注率アップの大きなヒントが見つかることがあります。ぜひ、地図を使った分析を試してみてくださいね。
"UPWARD"について資料をダウンロード
以下のフォームにご入力いただくと、ダウンロードURLを記載したメールをお送りします。